注記
※本記事は隔月刊誌『通所サービス&マネジメント 』2019年5-6月号に掲載の「介護スタッフが共感疲労に陥らないためのサポートのあり方〜感情労働の視点から」(執筆者:天理大学 人間学部 人間関係学科 社会福祉専攻 教授 松田美智子)より引用しています。
介護従事者と共感疲労
肉体労働や頭脳労働という用語はよくご存じかと思います。一般的には,肉体を駆使して賃金を得る仕事が肉体労働で,頭脳を駆使して賃金を得る仕事が頭脳労働と言 われます。では,感情労働という用語を耳にしたことはあるでしょうか? 感情労働とは,感情をめぐる高度なスキルを駆使して賃金を得る第三の労働のことです。職種によって単純に区分されるものではありませんが,介護という仕事には肉体と頭脳と感情の三者を駆使することが求められます。価値や倫理が強調される福祉専門職全般に言えることですが,直接かかわる相手が支援を必要とする存在であるが故に,支援者側に「何とかしてあげなければならない」という気持ちが募り,利用者の感情に必要以上に触れてしまう場合があります。そのため,誠実に向き合おうとすればするほど,「共感疲労」が存在する場合があります。
「共感疲労」とは,他者をケアすることから生じる支援者側の心理的疲弊のことを言います。つまり,誠実に利用者に向き合う介護従事者ほど「共感疲労」に陥りやすいと考えられます。
感情労働と感情管理
では,なぜこのようなことが起こるのかというと,介護職員をはじめとする高齢者介護福祉領域での対人援助職の仕事が,いわゆる「感情労働」だからです。感情をめぐる高度なスキルが要求され,感情を駆使する労働が「感情労働」です。武井は,看護の領域で感情労働について論考する中で,その概念を「感情労働とは,人々と面と向かって,あるいは声を通しての接触があり,職務内容のなかで感情が重要な要素となり,雇用者による訓練や指導監督を通じて働き手の感情面での活動をある程度コントロールされる」とし,患者に対して「自分の感情を掻きたてられたり抑えたりしながら働く」と分かりやすく説明 しています1)。
これは対象を利用者に読み替えれば,介護職員にも当てはまります。どんなに腹が立つことがあっても,怒りやイライラした感情を表面には出さず,あくまで相手の立場に立って共感的理解を示します。利用者の前では自らの感情をコントロールして対面するよう訓練され,身につけていくのが感情管理です。
感情管理がうまくいかないと自身の感情レベルの消耗感をもたらし,バーンアウトという燃え尽き症候群に至り,就労が継続しづらい状況に陥ることがあります。
感情労働はコミュニケーションを伴うことが特徴です。例えば,生活支援の提供過程において,介護職員らは利用者の状態や生活状況,あるいはニーズや気持ちの変化に対応して,生活支援の内容を調整・修正していくのであり,そこには,両者の適切なコミュニケーションが不可避の要素として存在します。
感情労働がこのような特質を有するが故に,介護職員らが自らの感情管理をうまくできない場合はストレス状況に曝されることになります。
2015年に,介護施設で働く相談員や介護職員,看護師などに対し,仕事を行う上でどのようなことにストレスを感じているのか,インタビュー調査2)を実施しました。その結果,介護施設で働いている対人援助職者には感情労働の実態があることが分かりました。インタビュー内容をすべて逐語録化し,感情労働に関する発話をカード化しました。そして,カード分類法によりカテゴライズし,グループごとに命名し表題を付けたものを図解化しました。その結果が図1です。
■関連ページ■


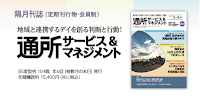
コメント
コメントを投稿